
 オンラインプログラム
オンラインプログラム


 オンラインプログラムOnline School
オンラインプログラムOnline School
【オンラインプログラム】食農教育のはじめかた
_page-0001-724x1024.png)
のコピー_page-0001-724x1024.png)
食農教育は、特別な人のためのものではありません
毎日のごはん、子どもとの会話、学校や地域での何気ないやり取り。
その中にある「気づきの種」を、学びへと育てていく。
まちの食農教育のオンラインプログラムは、
「すでにある日常」から、学びと実践を立ち上げるための時間です。
神山町で9年間、保育所から高校までの現場とともに育ててきた食農教育の実践をもとに、
・どこから始めればいいのか
・どう続ければいいのか
・自分の地域ではどう展開できるのか
を、立場や経験を問わず考えていきます。
「興味はあるけれど、まだ形になっていない」
そんな状態の方にこそ、ひらかれたプログラムです。
【基礎編】 まずは30分。食農教育の全体像と〝入口〟をつかむ時間
基礎編は、冊子『食農教育のはじめかた』をテキストに、
まちの食農教育が「何を大切にしてきたのか」「なぜ続いてきたのか」をぎゅっと30分に凝縮してお伝えするオンラインプログラムです。
実践のノウハウを一方的に学ぶというより、
「自分は何に引っかかっているのか」「どこに可能性を感じているのか」
を整理する時間になることを目指しています。
実践編への参加を検討されている方にとっても、考え方の土台をそろえる“ウォーミングアップ”としておすすめです。
\こんな人におすすめ/
・食農教育に関心はあるが、何から考え始めればいいか分からない
・本は読んだが、実践のイメージがまだつかめていない
・学校・地域・家庭をつなぐ学びに、ヒントがほしい
・実践編に進む前に、雰囲気や考え方を知っておきたい
日程
(予定は変更になる可能性もあります。随時こちらのページで更新していきます)
【第1回】 9月18日(木)19:00ー19:30(終了)
【第2回】 9月27日(土) 9:00ー 9:30(終了)
【第3回】10月 3日(金)20:00ー20:30(終了)
【第4回】11月 4日(火)15:00ー15:30(終了)
【第5回】11月15日(土)13:00ー13:30(終了)
【第6回】11月24日(月)20:00ー20:30(終了)※当初の予定から変更しています
【追加01】12月 3日(水)19:00ー19:30(終了)
【追加02】 1月 9日(金)19:00ー19:30(12/15 受付開始)
【第7回】 1月21日(水) 9:30ー10:00(12/15 受付開始)
【第8回】 2月20日(金)19:00ー19:30(1/7 受付開始)※当初の予定から変更しています
【第9回】 3月 6日(金)20:00ー20:30(2/3 受付開始)
※ いずれもオンライン30分 (アーカイブはありません)
※ 01〜09の内容は同じ内容でお送りする予定です。
参加費
冊子をお持ちの方: 無料
冊子をお持ちでない方: ¥2,410(税込)
※ 冊子のお届けに1週間程度を要しますので、日程に余裕を持ってお申し込みください。
定員
各回 10名程度 (最少催行人数:1名)
お申し込み方法
受付開始日になりましたら、peatixのページ からお申し込みください。
受付開始のアナウンスは、当団体 Facebook 、Instagram にて行います。
「基礎編」に参加された方の声
タイトな時間でしたが、お話を伺えてよかったです。
本で読むだけよりもハートが感じられて、「食農教育」って意義深く楽しい取り組みなんだなと思いました。(基礎編)
参加者の皆さんも年齢幅も広く、各地で色んな思いから参加されていて食農教育が認知されつつあることが実感できました。(基礎編)
【実践編】 「やってみたい」を「組み立てられる」に変える、3回の対話
実践編は、すでに活動している方、これから始めたい方が、自分の現場に持ち帰れる形で食農教育を設計することを目的とした90分3回コースのプログラムです。
神山町での実践事例をひもときながら、
・プログラムをどう組み立てるか
・学校や地域とどう関係をつくるか
・子どもたちの学びをどう捉えるか
を、参加者同士の対話を通して深めていきます。
最終回には、参加者それぞれの実践や企画を持ち寄り、「それぞれの場で続いていく形」を一緒に考える時間を設けます。
\実践編に参加すると得られること/
・自分の地域・学校・立場に引き寄せたプログラムの構想が描ける
・食農教育をESDの視点で捉え直す軸ができる
・同じ問いを持つ実践者とつながり、孤立しない感覚を得られる
日程
実践編は3回コースのプログラムです。
1日目(共通)食農教育のはじめかた/つづけかた/深めかた
2日目(各回)10月、12月、2月で中心テーマ(太字)を設定
3日目(共通)参加者による実践・企画の共有会と相互フィードバック【実践編 秋プログラム】学校で、種もみから育てる米づくり
1日目:10月10日(金)20:00ー21:30(樋口)
2日目: 17日(金)20:00ー21:30(植田)
3日目: 24日(金)20:00ー21:30
https://shokunoonline202510.peatix.com
【実践編 冬プログラム】身近な風景のあじわいかた
1日目:12月06日(土)10:00ー11:30(樋口)
2日目: 13日(土)10:00ー11:30(森山)
3日目: 20日(土)10:00ー11:30
https://shokunoonline202512.peatix.com
【実践編 春プログラム】ESDの視点でつくる食農プログラム (受付期間 12/15-2/4)
1日目: 2月15日(日)10:00ー11:30(樋口)
2日目: 2月22日(日)10:00ー11:30(須賀)
3日目: 3月 1日(日)10:00ー11:30
https://shokunoonline202602.peatix.com
ESDの視点を持つことがなぜ大切なのか?
ESDとは、Education for Sustainable Developmentの略称で、持続可能な社会を創るための教育枠組みです。学校教育での実践のみならず、誰しもがこれからの社会を創っていく担い手であるという考えのもと、その当事者性を育む生涯にわたる教育として重要視されています。
私たちは、食農教育による学びを見える化させるオリジナルルーブリック「学び上手になるロードマップ」を設計して、ESDの観点で捉える食農教育の可能性を示唆しています。
食農プログラムに取り組む子どもたちが、身体感覚を伴う実体験を積み重ねていくことで培っていく思考や態度を、やがて持続可能な社会を自ら創る力へとつなげていく、そんな未来を描いています。
本講座では「学び上手になるロードマップ」の説明を織り交ぜながら、食農プログラムにESDの視点を組み込んでいく工夫をお伝えしていきます。
参加費
冊子をお持ちの方: ¥27,500(税込)
冊子付き : ¥30,000(税込)
定員
10名
(最少催行人数:3名)
お申し込み方法
受付開始日になりましたら、peatix からお申し込みください。
受付開始のアナウンスは、団体の Facebook、Instagram にて行います。
※ アーカイブ動画、当日使用したレクチャー資料は後日共有します。
オンラインプログラム(実践編)に参加された方の声
教えてもらう、というより、自分の中にある課題や想いを引き出し、整理し、エンパワーしてくれる、そんな素敵な講座です。この出会いが、新しい一歩を踏み出すきっかけになるかもしれません。(実践編)
漠然とでも全然よいので食農教育をやってみたい、興味があるという方へぜひおすすめしたいです。神山町の事例を踏まえたうえで、では自分のところではどうやってやれそうか、やってみたいか、考えることのできるきっかけになると思います。(実践編)
スピーカー
オンラインプログラム(実践編)に登場するメンバーを紹介します。
氏名/経歴/食農教育を一言で表すと?/オンラインプログラムへの意気込み

樋口 明日香(まちの食農教育 代表理事)
神奈川県で小学校教諭として14年間勤務。在職時には教育相談(特別支援教育)コーディネーターとして5年間、医療・心理の専門職と連携し、子どもの周辺環境の調整役を担う。
2010年から通い始めた白崎茶会で「認定パン先生」の資格を取得ののち、2016年に徳島にUターンし、フードハブ・プロジェクトに参画。2022年より現職。
食べ物を「そだてる」経験を通して周辺環境を見る目を養えるのが食農教育。オンラインでつながる方々と実践を共有しながら高め合う場をつくる試み、とても楽しみです。

植田 彰弘(まちの食農教育 理事)
2012年より神山町在住。「日々の積み重ねが地域の風景を育む」を理念に同町江田集落の棚田保全活動に参画。集落の農村文化を尊重し、約1ヘクタールの耕作放棄地を管理・再生。自然環境に負荷をかけない農法を実践しながら、稲作を中心とした生活を営んでいる。
食農教育は未来の食卓に〝選択〟という彩りを加えることができる取り組みだと感じています。
子どもたちが育んだ農体験から彩られる未来の食卓をみんなで考えていきましょう。

森山 円香(まちの食農教育 理事)
神山町の創生戦略の策定に関わった縁で2016年より同町在住。町内の農業高校のカリキュラム開発やスクールポリシーの策定など学校と地域をつなぐコーディネートに奔走。現在は1歳児を育てながら京都大学大学院地球環境学舎に通う。新米ハンター。著書に『まちの風景をつくる学校 ー神山の小さな高校が試したことー』(晶文社)。
私たちの日々の食の選択が、巡り巡って風景として立ち現れてくる。そんなことを頭ではなく身体で理解してしまう力が食農教育にはあると思います。それぞれの土地で活動している・しようとしている方々とお会いできることを楽しみにしています。

須賀 智子(まちの食農教育 理事)
食を専門とするメディア・料理通信社で「つくり手(生産者)・つかい手(料理人)・食べ手(生活者)」を結ぶことをスローガンに、食を取り巻く社会・環境問題の取材活動、食×SDGsカンファレンスの企画運営等を行う。独立後、食をテーマにした教育コンテンツ開発・ワークショップ設計に携わる。業務の傍ら、食を起点にしたESD(持続可能な社会を創るための教育)デザインの研究を続ける。慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究所SDM研究員。
ESDのレンズを通して食農教育の可能性を探ることは、〝おいしい〟が続く未来をつくるチャンレジ。ぜひご一緒ください。
学びあうラーニング・コミュニティ
一方通行の講義ではなく、インタラクティブに学びあう少人数制のオンライン講座です。食と農をテーマに各地で活動している人たちとの出会いは貴重なものになるはずです。
オンラインプログラムの終了後にも、神山町でのフィールドワークや交流会などの企画、2026年にはスクールフード・フォーラムの開催も予定しています。
プログラムをきっかけに、今後も長く交流を重ねていけるとうれしく思います。
最後に
わたしたちは、食農教育の推進役に「スクールフード・コーディネーター」と名称をつけました。農家、料理人、学校の先生(担任、栄養教諭)、お父さん、お母さん、保育士など、多様な方々が「スクールフード・コーディネーター」の役割をもつことで、食農教育の幅は広がっていくように思います。
ごくごく身近な食べ物から「周辺の見え方、楽しみ方」に触れられるのが、食農教育の良さ。
例えば、わたしたちの活動場所である神山町は、山に囲まれ、東西に川が走る山あいのまち。
食べものを育てると、土地の履歴、地域の歴史、食文化、周辺環境の変化にも気づかされます。そしてなにより、大先輩から教わる所作は、地域の資源を有効に使い尽くす知恵と工夫に満ちています。「理にかなう」という体験を含めて、食べ物づくりと地域の景観とのつながりが見えやすくなります。
みなさんが暮らす地域やコミュニティでは、どうでしょうか。
プログラムを通じて、他の地域の皆さんとお会いできることを楽しみにしています。そして、それぞれの今いる場所で、活動を進めていきましょう。

参考
・まちの食農教育「そだてる、まなぶ、たべる」をつなげる学校食(YouTube)
・School Food Forum 2023【ダイジェスト】(YouTube)
【終了】スクールフード・コーディネーター養成講座受講生募集(モニター開催)
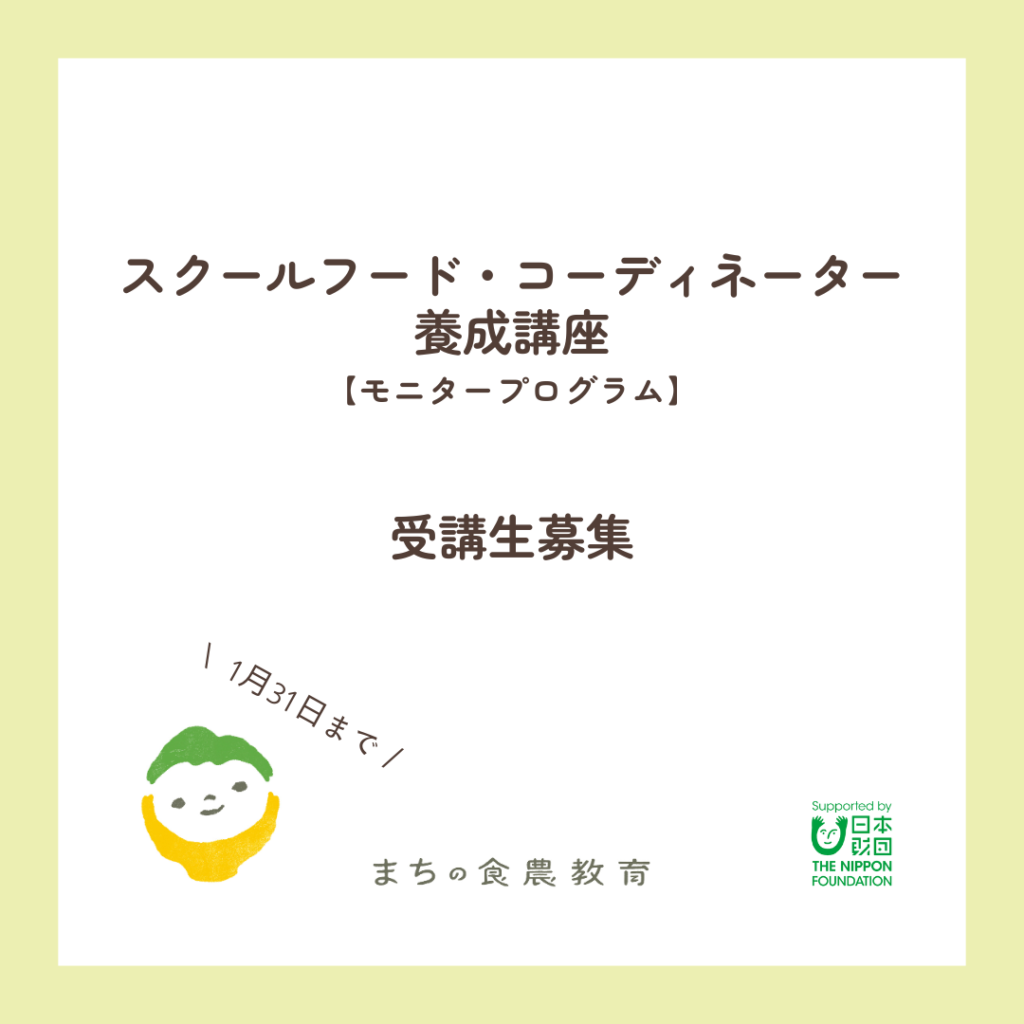
まちの食農教育では、食農プログラムを実践する人たちをサポートするための取り組みとして、オンライン講座をはじめます! まずは2〜3月にかけてモニター版を実施します。関心のある方はぜひお申し込みください。
私たちがこれまで実施してきたプログラムは、「そだてる」「あじわう」「つなぐ」体験を軸に、身体と心と頭をめいっぱい動かしながら、社会への眼差しと自身の可能性を育んでいくプログラムです。
子どもたちにプログラムを届ける人を『スクールフード・コーディネーター』と呼び、今回の養成講座でもその役割についてお伝えしていきます。スクールフード・コーディネーターは、学校や地域の風土を尊重し、食を中心にした学びをコーディネートする人です。誰もが担いうる役割の名称で、学校の先生、栄養士、料理人、生産者、地域コーディネーター、お父さんお母さんなど、子どもたちと関わる人は誰だってスクールフード・コーディネーターになりえます。また、食農プログラムは学校との連携に限ったものでなく、地域のコミュニティの中で実践することもできます。
本講座では、まちの食農教育が9年間に渡り、のべ900人を超える子どもたちにプログラムを届けてきた経験を元に、プログラムのつくり方や多様な人々と協働する際のポイントをお伝えします。
食農をテーマにした学びの場を開きたい方や深めたい方のご参加をぜひお待ちしております。
講座の内容
食農プログラムのはじめかた
子どもたちと学ぶ場をつくりたいと思ったとき、どこからはじめたらいいのでしょう。徳島県神山町で食農プログラムが生まれた背景や変遷を辿りながら、現在の食を取り巻く課題や食農教育の意義について一緒に考えます。
食農プログラムのつくりかた
企画の立て方、運営方法、スクールフード・コーディネーターの役割、関係者とのやりとりなど、いざプログラムをつくるとなると考えることはたくさんあります。これまでの取り組みを踏まえて、うまくいったポイントや私たちが気をつけていたこと、失敗から学んだことも惜しみなくお伝えします。
食農プログラムのふかめかた
単発のイベントから日常的な活動へ。一人のアイデアからみんなの取り組みへ。年間計画の立て方やルーブリックの活用など、プログラムの質を高めていく工夫について実践していることをお話します。
講座の特徴
学びあうラーニング・コミュニティ
一方通行の講義ではなくインタラクティブに学びあう少人数制のオンライン講座です。食と農をテーマに各地で活動している人たちとの出会いは貴重なものになるはずです。
※ アーカイブ動画を共有しますので、リアルタイムの参加が叶わない方もご参加いただけます。
修了後のサポート
講座を終えてからがみなさんにとっての本番です。オンラインコミュニティでの情報交換や、まちの食農教育や関連組織でのインターンなど、講座修了後にみなさんの活動がうまくいくよう応援していきます!
講座の日程
1.2月19日(水)19:00-20:30
オリエンテーション・食農プログラム理論編
2.3月5日(水)19:00-20:30
食農プログラム実践編
3.3月19日(水)19:00-20:30
食農プログラム未来編・振り返りセッション
・副読本として団体発行冊子「食農教育のはじめかた」を受講者全員にお渡しします(3月末の発行を予定しているため、講座終了後のお渡しとなります)。
・リアルタイムの都合がつかない方は、後日お送りするアーカイブ動画でご視聴いただけます。
定員
8名
受講料 ※ モニター価格
15,000円(25歳以下 7,500円)
申込方法
お申込フォームよりお申し込みください。→ お申込フォーム (1/22時点で満席となり、お申し込みの受付を終了しました。4月以降の開催は団体ホームページでご案内します)
募集期間
2025年1月31日(金)まで
お申し込みいただいた方へ支払い方法をご案内します。支払い完了で参加申込完了とさせていただきます。
メッセージ
食農プログラムの実践者が増えることは、食べ物づくりを通して地域の第一次産業の理解者が増えたり、食べ物の選び方が変わったり、まちを見る目が育っていく、その土壌をつくっていくことだと考えています。学び場をともにつくっていく仲間を広げていきたいと考え、現在「食農教育のはじめかた」という冊子を制作中です。このオンライン講座は、その冊子を手にした方が「歩きかた」を学ぶ講座と考えています。わたしたちのこれまでの活動を共有しながら、各地の実践を後押しできればと考えています。
講座修了後、引き続き各地で取り組みを進めていく皆さんとの情報交換の場をつくっていけるよう、オンラインコミュニティを立ち上げます。ここでは私たちが神山町で実践してきたプログラム企画書(指導案)を閲覧いただけるようにする予定です。
ほかにどのようなサポートがあると皆さんの実践を応援できるだろうかと考えています。
例えば、皆さんの地域で食農教育について考える場を開きたいというニーズがあるならば、わたしが出向いて神山町の事例をお話しさせてもらいます。プログラム運営の経験をしたい方には、神山で開催しているプログラムにゲスト スクールフード・コーディネーターとして登場いただく機会もつくれそうです。はたまた農業や飲食の分野でインターンをしたい! なんてご相談もお受けできそうです。
皆さんの関心や地域の状況を踏まえて、一緒に考えていきたいと思います!
まちの食農教育 代表 樋口 明日香
